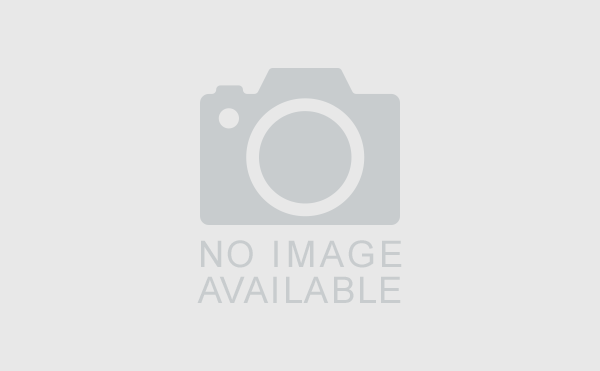養育費はいくら?どう決める?|2024年法改正と算定表のポイント
離婚や別居を考えたとき、「子どもの養育費はどうすればいいの?」と不安に思う方は少なくありません。
養育費は、お子さんの生活を支える大切なお金。けれど、「どうやって決めるの?」「相場ってあるの?」「ちゃんと払ってもらえるの?」など、疑問や心配は尽きませんよね。
このページでは、養育費の基本から、2024年の法改正で明確になった“生活保持義務”、そして実際の金額の決め方や取り決め時の注意点まで、わかりやすく解説しています。
専門的な知識がなくても大丈夫です。お子さんの未来を守るために、いま何ができるのか――。一緒に確認していきましょう。
第1章:養育費ってどう決めるの?──最初に知っておきたい基本
離婚を考え始めたとき、まず気になるのが「子どもの養育費はどうすればいいの?」ということではないでしょうか。
お金の話はしづらいものですが、養育費は、これからのお子さんの生活を守る大切な柱になります。
● 養育費とは、「子どもが自立するまでの生活費」
養育費とは、離れて暮らす親が、子どもを育てている親に支払う「子どものためのお金」です。
食費、衣類、教育費、医療費など、子どもが暮らしていくために必要なあらゆる費用が含まれます。
よく「相手に使われそうで払いたくない」と言う人もいますが、養育費は親同士の問題ではなく「子どもの権利」です。
子どもにとって必要なものをきちんと受け取れるように、しっかり考えていく必要があります。
● 養育費は、まず「話し合い」で決める
養育費の金額や支払い方法は、原則として夫婦の話し合いで決めます。
離婚のときに「○万円を何歳まで払う」といった内容を決めて、書面に残すのが一般的です。
ただし、話し合いがうまくいかなかったり、金額の相場が分からなかったりすることもあります。
そんなときは、裁判所が作った「養育費算定表」という目安を参考にしたり、専門家に相談することで、客観的な金額を決めることができます。
● 現実には「払わない人」も多い
残念ながら、養育費は取り決めをしても、支払われなくなるケースが少なくありません。
厚生労働省の調査では、「養育費を継続して受け取れているひとり親世帯」は全体の約2割程度にとどまっています。つまり、「もらえると思っていたのに、もらえない」ことも多いのが現実です。
だからこそ、最初の話し合いと取り決めの方法が、とても重要になってきます。
第2章:2024年の法改正で何が変わった?──生活保持義務とは
2024年の法改正により、親の「養育費の義務」がこれまでよりも明確になりました。
これまでも親には養育費を支払う義務があるとされてきましたが、今回の改正で“どれくらいの生活レベル”を保障すべきかが、はっきりと法律に書かれたのです。
● 親は子どもに「同じくらいの生活」をさせる義務がある
改正された民法では、親には「生活保持義務」があるとされました。
これは、離れて暮らしていても、自分と同じくらいの生活レベルを子どもにも保障しなければならない、という考え方です。
たとえば、自分が会社員として安定した収入を得ていれば、子どもにもそのレベルの暮らしができるよう、養育費を支払う責任があるということです。
● これまでの「生活扶助義務」とはどう違う?
以前は、主に「生活扶助義務」と呼ばれる考え方が使われていました。
これは「最低限の生活を支える」程度の意味合いで、親の収入が多くても、それに見合った養育費を払わないケースも見られました。
ですが、「生活保持義務」が明文化されたことで、子どもは親と同等の生活水準を求める権利がある、という強いメッセージになったのです。
● 明文化された意味はとても大きい
今回の改正は、現実の「払わない親」や「低すぎる養育費」といった問題に対して、国がはっきりと姿勢を示したという点で、とても重要な意味を持っています。
法律に明記されたことで、養育費をめぐる話し合いの場でも「親と同じくらいの生活を子どもに」という考えを根拠として示すことができます。
裁判になったときの判断基準にもなりうるため、養育費を受け取る側にとって、心強い追い風と言えるでしょう。
第3章:養育費の“金額”はどう決まる?──算定表の使い方と注意点
養育費の金額を決める際に、多くの方が参考にするのが「養育費算定表(よういくひさんていひょう)」です。
これは、家庭裁判所でも使われている“目安”の表で、収入と子どもの人数・年齢に応じた相場が示されています。
● 養育費算定表とは?
算定表とは、「夫婦の年収」と「子どもの人数・年齢」を掛け合わせることで、だいたいの養育費の目安が分かる早見表です。
たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円、子どもが1人(0〜14歳)なら、養育費は毎月◯万円程度、というふうに示されています。
裁判所での調停や審判でも、この算定表をもとに判断されることが多く、「公平で納得しやすい」金額を話し合う材料になります。
● 収入の見方に注意!源泉徴収票だけでは分からないことも
算定表を使うときのポイントは、「収入の見方」です。
自営業なのか会社員なのか、源泉徴収票のどの項目を見ればいいのか──細かいルールがあります。
たとえば、会社員の場合は「税込み年収(総支給額)」が基準になりますが、自営業の場合は「課税所得」が基準になるため、少し注意が必要です。
この「課税所得」は、実際の経費や控除が反映された後の金額ですので、経費の水増しや控除の取り扱いによって、見かけの所得が変わるため、注意が必要です。
また、ボーナスが多い人や、副業収入がある場合なども、算定額に影響することがあります。
● 2019年の改訂で“少し増額”された
実は、算定表は2019年に見直され、それ以前よりも養育費の金額が少し引き上げられました。
物価や教育費の上昇を踏まえ、より実情に合った内容になったとされています。そのため、以前の古い算定表を参考にしていると、相場より低い金額で合意してしまうことも。
必ず最新の表を使い、今の生活実態に合った金額で取り決めることが大切です。
第4章:取り決めは“書面化”がカギ──公正証書と協議書の違い
養育費の話し合いが終わったら、それでひと安心……と言いたいところですが、実はここからがとても大事なステップです。
取り決めた内容を「きちんと書面に残すこと」。これが、養育費を確実に受け取るためのカギになります。
● 口約束では守られない。だから書類が必要
「毎月○万円払うって言ってたから大丈夫」と思っていても、口約束ではいざというときに証明できません。
たとえば、支払いが止まったとしても、約束が書類になっていなければ、裁判所に申し立てることも難しくなります。
後々のトラブルを防ぐためにも、養育費の金額や支払い方法、期間などを明記した「協議書」や「公正証書」を作成しておくことが重要です。
● 「協議書」と「公正証書」のちがい
協議書とは、当事者同士の合意内容を文書にまとめたものです。
ただし、これはあくまで“私的な契約”なので、支払いが滞った場合に強制力はありません。
一方で、公正証書は「公証役場」で作成する正式な書類です。
公証人という法律の専門家が関与して内容を確認してくれるため、信用性が高く、法的効力もあります。
特に、養育費の支払いが心配な場合は、公正証書にしておくことで将来の安心感が大きく違ってきます。
● 強制執行認諾文言ってなに?
公正証書には、「強制執行認諾文言(ごうせいしっこう にんたくもんごん)」という一文を入れることができます。
これは簡単にいうと「払わなかったときは財産を差し押さえてもいいです」と、あらかじめ認めておく内容です。
この文言があると、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料や預貯金に対して“強制執行”ができるようになります。
つまり、「払わない」という選択肢を取らせないための強力な手段なのです。
第5章:「払われない」を防ぐ工夫──遅延損害金・保証人の設定
養育費の取り決めをして、公正証書も作った。
でもそれでも、「途中で支払いが止まったらどうしよう……」という不安は消えませんよね。
実は、そうした“もしも”に備えておく方法がいくつかあります。
● 養育費が止まるリスクに備える
厚生労働省の調査によると、養育費を取り決めたにもかかわらず「継続して受け取れているひとり親世帯」は、わずか2割程度。
途中で支払いが途絶えてしまうケースがとても多いのが現実です。
だからこそ、公正証書にしておくことはもちろん、「払われなかった場合の備え」をあらかじめ盛り込んでおくことが大切です。
● 遅延損害金を入れておく意味
「遅延損害金」とは、支払いが遅れたときに追加で発生する“ペナルティ”のようなお金です。
たとえば「支払いが1日でも遅れたら、年〇%の利息をつけて請求する」という文言を入れておくことで、抑止力になります。
実際には、この利息を請求しないこともありますが、「遅れたら損をする」という意識を持ってもらうだけでも、支払いの継続につながることがあります。
● 連帯保証人は本当に有効なのか?
「連帯保証人を立ててもらう」というのも、一つの方法です。
保証人がいれば、養育費が払われなくなったときに、その人に請求することができます。
ただし、保証人を立ててもらうのは現実にはハードルが高いことも多く、相手が拒否する場合もあります。
それでも、支払いに不安がある場合や、過去にトラブルがあったケースでは、選択肢として検討する価値があります。
また、保証人をつけることで、「本気で責任を持って払う意思があるのか」を見極める一つの材料にもなるでしょう。
第6章:安心のためにできること──迷ったら誰に相談する?
ここまで読んで、「わかったつもりだけど、うちはどうしたらいいんだろう?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
養育費の取り決めは、法律、実務、そして相手の性格や状況なども絡み合うため、一人で判断するのがとても難しい問題です。
● 専門家に相談することは、“迷い”を減らす第一歩
誰に相談すればいいのか迷っている方へ、まず大切にしていただきたいのは「信頼できる専門家に、今の悩みをそのまま話してみること」です。
ネットの情報だけでは、自分のケースにぴったり合う答えを見つけるのは難しいもの。
だからこそ、早めに相談することが、不安を減らす第一歩になります。
● 行政書士・弁護士・カウンセラー、それぞれの役割
- 弁護士: 相手との交渉や裁判が必要なときに。強制力のある対応が求められる場面で頼れる存在です。
- 行政書士: 合意内容を「文書にまとめる」サポートが専門。たとえば、養育費の取り決めを書面化したり、公正証書に必要な準備をお手伝いしたりと、“書類面の支え”に強みがあります。
- カウンセラー: 感情面の整理や、相手との関係性の悩みなど、法律以外の部分での支えに。心の整理がつかないときは、まずここから始めるのも一つの選択肢です。
それぞれ得意分野が異なりますので、いま自分が「どこにつまずいているのか」に合わせて相談先を選ぶのがコツです。
● 大事なのは、「話しやすい人」と出会うこと
どんなに専門知識があっても、「自分の話をきちんと聞いてくれる人」じゃないと、相談は前に進みません。
家庭のこと、子どものこと、お金のこと。すべて話すには、安心できる相手であることがとても大切です。
たとえば私たち行政書士は、書類作成の専門家でありながら、家庭の状況に寄り添いながら一緒に考えてくれる存在でもあります。
● 未来の安心のために、“今”できる準備を
養育費の問題は、子どもの未来に直結する大切な課題です。
完璧な答えがすぐに見つからなくても、「どうすれば守れるか」を考え始めたその一歩が、未来を変える大きな力になります。
困ったときは、どうか一人で抱え込まず、あなたに合った相談先を見つけてください。
そして、必要な準備を少しずつでも始めていきましょう。
あとがき:子どもを守るために、いまできることを
養育費の取り決めは、ただの「お金の話」ではありません。
それは、将来の安心をつくるための大切なステップであり、親としての責任を果たす行動でもあります。
離婚や別居が決まっていなくても、もしものときに備えて「知っておく」「話し合っておく」ことは、とても大切です。
そして、その一歩を踏み出すのに、遅すぎるということはありません。
不安なときは、誰かに相談してみてください。
「一人で全部やらなきゃ」と思わなくても大丈夫です。
あなたと、あなたのお子さんのこれからが、少しでも穏やかで安心できるものになりますように。
離婚公正証書や協議書の作成は、経験豊富な行政書士にお任せください。
横浜の事務所、または全国オンライン相談でお受けしています。