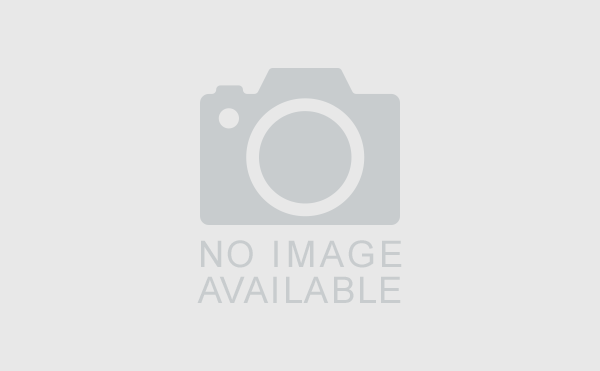養育費はどう変わる?法改正と生活保持義務のポイント解説
第1章:生活保持義務とは?
――子どもの「当たり前の生活」を守るために
離婚を考えたとき、まず心配になるのは、お子さんの生活ではないでしょうか。
「養育費って、いくらもらえるんだろう…」
「ちゃんと払い続けてもらえるのかな…」
そんな不安を抱える方に、ぜひ知ってほしい大切な考え方があります。
それが、**「生活保持義務」**という言葉です。
これは、親が子どもに対して、たとえ離れて暮らしていても「自分と同じくらいの生活をさせてあげる」責任のこと。
毎月25万円で暮らしているなら、子どもにも同じような生活ができるよう、それ相応の養育費を払う義務があるという考え方です。
この義務は、兄弟や親などに対する「生活扶助義務」よりも、ずっと強く、優先されるもの。
「自分に余裕があれば払う」のではなく、**たとえ生活が苦しくても“親として当然に果たすべき責任”**なのです。
養育費は、“気持ち”で払うものではありません。
子どもにとっての当然の権利であり、親に課された義務です。
その根っこには、子どもの健やかな生活を守りたい――
そんな、親としての大切な想いがあることを忘れないでください。
第2章:生活保持義務と生活扶助義務の違い
――「親としての責任」は、他の扶養とは違います
養育費について話していると、よく出てくるのが**「生活保持義務」と「生活扶助義務」**という2つの言葉です。
どちらも“家族を支えるための義務”ですが、その中身と重みはまったく違います。
とくに、子どもへの養育費の根拠となる「生活保持義務」は、特別に強い責任とされています。
■ 生活保持義務とは?
親が未成年の子どもに対して負う強い義務です。
ポイントは、**「自分と同じくらいの生活をさせる」**という点。
親に経済的な余裕があるかどうかではなく、親と同じ水準の生活を保障することが前提とされます。
養育費の金額も、この「生活保持義務」に基づいて算定されるのです。
■ 生活扶助義務とは?
一方、生活扶助義務は、兄弟姉妹や親子(子が成人している場合)などの間にあるものです。
こちらは**「最低限の援助」にとどまり、あくまで“余裕があれば”というスタンス**です。
■ 大きな違いをまとめると
- 親 → 未成年の子ども:生活保持義務(同じ生活レベルを保障)
- 兄弟姉妹・高齢の親など:生活扶助義務(最低限の援助、余裕があるときのみ)
この違いを知っておくと、**「養育費は親にとって避けられない大きな責任」**であることがよく分かります。
「生活が苦しいから養育費は払えない」
――それは、生活保持義務の考え方では通用しないのです。
親である以上、たとえ離れて暮らしていても、
子どもに“親と同じ水準の生活”を保障するのが当然の責任。
それが、養育費に込められた意味なのです。
第3章:2024年の民法改正でどう変わった?
――「養育費は親の責任」が法律に明記された意味
「養育費、きちんと払ってもらえるのかな…」
離婚を考えたとき、多くの方がぶつかる不安です。
実は、そんな悩みを少しでも減らすために、2024年5月に民法と民事執行法が大きく改正されました。
とくに注目すべきは――
✅ 生活保持義務が法的に明文化されたこと
✅ 「法定養育費制度」という新しい仕組みができること
✅ 差押えがしやすくなったこと
ここでは、改正ポイントをやさしく解説しながら、「これから離婚を考えている人」にどんな影響があるのかを見ていきます。
1.生活保持義務が法律に明記された
これまで「生活保持義務」は法律上の用語ではなく、判例や実務の中で使われてきた言葉でした。
それが今回、民法で初めて正式に定義されました。
「子どもが親と同程度の生活水準を維持できるように扶養しなければならない」
という表現で、親の当然の責任として明文化されたのです。
これにより、養育費は「気持ちで払うもの」ではなく、
法律に基づく“義務”としての性格がいっそう強くなりました。
2.「親の責任」が4つの柱として整理された
改正民法では、親の責任が明確に4つに分けられました。
- 子どもの人格の尊重
- 子どもの扶養(=生活保持義務)
- 父母間の人格尊重と協力義務
- 子どもの利益のための親権行使
このように、**養育費の支払いも“子どもの権利を守る親の責任の一部”**として位置づけられたのです。
3.「法定養育費制度」が創設される予定(2026年までに施行)
これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしないと、あとから請求するのが非常に大変でした。
今回の改正では、それを防ぐために法定養育費制度が新設されます。
これにより――
- 離婚時に養育費の取り決めがなくても、法定額で請求できるようになる
- 相手が払わなければ、差押えなど強制執行ができる
- 金額は「養育費算定表」に基づき標準化される見込み
つまり、「話し合いがうまくいかなかったから…」で終わらせずに、
制度として子どもを守る仕組みが整っていくのです。
養育費の取り決めは、やはり事前の書面化が重要です。
公正証書で確実に備える方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
4.養育費の差押えがしやすくなる(民事執行法の改正)
これまでは、裁判所の手続きや証拠の準備が大変で、差押えが現実的に難しいという問題がありました。
改正では、以下のような差押えしやすい仕組みが整備されます。
- 先取特権が認められ、私文書でも差押えが可能に
- 裁判所が相手の収入情報を開示させる命令を出せるように
- 手続きの一括申請(ワンストップ制度)も導入予定
これにより、「払ってもらえるか不安」から「払わせられる安心」へと、大きな変化が生まれようとしています。
今から意識したいポイント
これらの法改正は、2026年5月までに順次施行される予定ですが、
今、離婚を考えている人にとっても無関係ではありません。
なぜなら、法改正の流れを知っておくだけで――
- 離婚協議書や公正証書にどんな内容を盛り込めばいいかが明確になる
- 交渉で不利にならない視点が得られる
つまり、「どうせ払ってもらえないかも…」と諦めるのではなく、
制度を味方につけて、子どもの未来を守る備えができるのです。
第4章:養育費を確実に受け取るための準備とは?
――離婚前に整えておきたい「書面」と「条件」
「払ってくれるって言ってたのに…」
「最初は約束してくれたのに、いつの間にか連絡も取れない…」
養育費に関するトラブルは、多くの場合、**「離婚前の準備不足」**が原因です。
ここでは、離婚前にやっておくべき3つの準備について、わかりやすく解説します。
1.養育費の取り決めは必ず「書面」で残す
まず絶対に外せないのが、「養育費の取り決めは口約束ではなく、必ず書面にする」ことです。
口約束だけだと――
✔ 「そんな話はしていない」と言い逃れされる
✔ 証拠がなく、裁判や差押えが難しくなる
そこでおすすめなのが、公正証書にしておくこと。
特に、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」という文言を入れることで、
支払いが止まったときにすぐ給与や預金を差し押さえることができます。
公正証書=「いざというときに効く最強の契約書」
安心して離婚後の生活をスタートさせるためにも、まずは書面化を第一に考えましょう。
2.条件に不安があるなら「保証人」や「遅延損害金」を検討
相手の収入や誠実さに不安がある場合、以下のような追加条件でリスクを減らせます。
- 保証人をつける
→ 相手が払えなくなった場合、保証人に請求できるようにする - 遅延損害金の条項を入れる
→ 支払いが遅れた場合、一定の利息を追加で請求できる
これらは“万が一”への備えであり、**「払わせる抑止力」**になります。
最初は「ちゃんと払うよ」と言っていても、数年後に状況が変わることは珍しくありません。
将来のトラブルを防ぐには、「今のうちに整えること」が最大の保険です。
3.支払いが止まったときの「備え」も離婚前に整えておく
「もし払われなくなったらどうしよう…」という不安は、みなさんが抱えるリアルな悩みです。
でも大丈夫。備えがあるかどうかで、その後の安心感が大きく変わります。
- 公正証書があれば、裁判をせずに差押えが可能
- 遅延損害金の取り決めがあれば、遅れた分もきちんと請求できる
- 保証人がいれば、相手が行方不明・無職になっても対応できる
これらはすべて、離婚前にしか整えられない大事な備えです。
書面で整えることは、子どもの生活を守るための準備
養育費の取り決めは、「揉め事を避けたいから書かない」ものではなく、
子どもの未来を守るために“きちんと書いておく”ものです。離婚後は、あなたとお子さんの新しい人生のスタート地点。
不安を少しでも減らすために、冷静に、そしてしっかり準備を整えていきましょう。
第5章:法改正は“これから離婚する人”にも関係ある?
――2026年施行予定の民法改正をいまから活かすには
「まだ法律が変わるのは先の話だから、自分には関係ない」
そう思っていませんか?
でも実は、2026年までに施行される養育費に関する民法の改正は、
いままさに離婚を考えているあなたにも、大きく関係してくる内容なんです。
少し先の未来を知っておくだけで――
✅ 離婚協議で損をしない
✅ 公正証書に入れておくべき項目が見えてくる
✅ 条件交渉の“強い材料”になる
この章では、「どんな改正があるのか」「どう活かせるのか」を、やさしく解説していきます。
1.生活保持義務が法的に明文化された
これまで、「子どもに親と同じ生活水準を保障すべき」という生活保持義務は、裁判所の解釈で運用されてきました。
ですが、2024年の改正で、
「親は、子どもが自分と同じ生活水準を維持できるように扶養しなければならない」
という内容が、法律にしっかり書き込まれました。
つまり、「余裕がないから…」「最低限でいいでしょ」は通用しません。
これにより、養育費の交渉でも――
**「子どもには“当たり前の生活”を受け取る権利がある」**という根拠が明確になったのです。
2.「法定養育費制度」が新設される予定(2026年施行)
離婚時に養育費の取り決めができなかった場合、
あとから請求するのはとても大変でした。
でもこれからは、取り決めがなくても法定で請求できる仕組みが整います。
それが「法定養育費制度」です。
- 調停や審判をしなくても、決められた金額を請求できるようになる
- 金額は「算定表」に基づき、一定の基準で統一される予定
- 支払われない場合は、差押えなどの強制執行も可能に
つまり、「泣き寝入り」が当たり前だった時代から、
「制度として子どもを守る時代」へと変わろうとしているのです。
3.「いま離婚協議中」でも交渉カードとして使える
この法改正、実は今まさに離婚の話し合いをしている人にとっても、強い味方になります。
たとえば――
「2026年にはこの金額が“法定基準”になるから、今からそれに合わせましょう」
「あとから差押えできる制度が始まるので、今のうちに公正証書を作っておきましょう」
こうした情報を知っておくだけで、不利な条件を避けたり、納得できる形で合意しやすくなります。
相手が法律の改正を知らない場合でも、
あなたの方が一歩リードできるチャンスです。
4.「あとからでは遅い」を避けるために
離婚協議や条件交渉は、一度終わってしまうとやり直しができません。
「あのときもっと調べておけばよかった…」
「不利な内容でサインしてしまった…」
そうならないためにも、今から知識を得ておくことが何より大切です。
未来の制度を知っておけば、準備の質が変わります。
準備の質が変われば、離婚後の安心感も変わります。
離婚は「準備次第」で大きく変わる
新しい制度がスタートしてから考えるのでは遅すぎます。
先に知ること、今から備えることで、未来の選択肢が広がります。どうか、あなたとお子さんの生活を守るために、少しだけでも冷静に、今できる準備を整えていきましょう。
最終章:未来の不安を「安心」に変えるために
――養育費をめぐる正しい知識と心の準備をあなたへ
離婚を考えたとき、誰もが不安になります。
とくに、子どもを育てていくこと、そして養育費のこと。
「本当に払ってもらえるのか」
「途中で止まったらどうしよう」
そんな思いに、押しつぶされそうになることもあると思います。
でも、どうか覚えていてください。
あなたの不安は、あなただけのものではありません。
多くの方が、同じように悩みながら、それでも前に進もうとしています。
養育費は“お願い”ではなく、“子どもの権利”です
「もう、いらないって言ってしまおうか」
「面倒だから話し合いをやめてしまおうか」
そう思ってしまうことがあっても、決して弱さではありません。
でも、養育費は“あなたのお願い”ではなく、
**お子さんが受け取るべき当然の“権利”**です。
その権利を守れるのは――
他でもない、あなたです。
書面で残すことが、未来の安心につながる
たとえ、どんなに良い条件を話し合えても、口約束では守られません。
それを防ぐために、公正証書や離婚協議書など、書面で備えることが必要です。
そして今、制度も少しずつ変わり始めています。
払われない養育費を「仕方ない」で終わらせないよう、
**制度の力で“払わせられる時代”**が来ようとしています。
知識を持つこと。備えること。
それが、あなた自身とお子さんを守る力になります。
迷ったら、一人で抱え込まないで
法律や制度、交渉のこと……
すべてを一人で完璧に理解する必要はありません。
わからないことがあって当然です。
でも、「子どもを守りたい」というあなたの気持ちこそが、何よりの力です。
不安なときは、信頼できる専門家を頼ってください。
あなたが安心して一歩踏み出せるよう、
力になってくれる人は、きっといます。
あなたとお子さんの未来に、安心と笑顔を
離婚は、人生の終わりではありません。
新しい人生の始まりです。
どうか、自分を責めないで。
焦らなくて大丈夫。
ひとつずつでいいから、いま自分にできることを整えていきましょう。
あなたの選択が、
あなたとお子さんの未来を、きっと明るいものにしてくれます。
心から、応援しています。
離婚公正証書や協議書の作成は、経験豊富な行政書士にお任せください。
横浜の事務所、または全国オンライン相談でお受けしています。