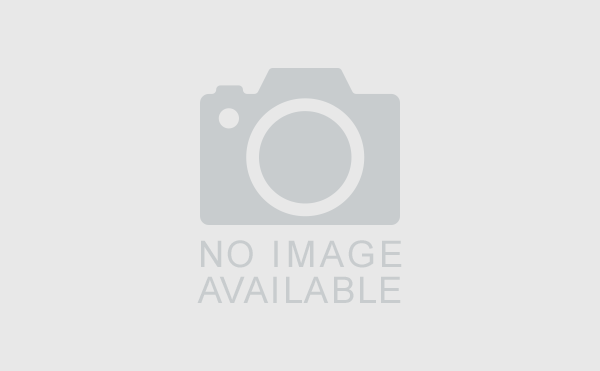離婚しても家に住みたい
“夫名義のまま”で起こるトラブルと公正証書の備え
第1章:離婚後も、夫名義の家に住み続けたい——それって可能?
「離婚しても、子どもと一緒に今の家に住み続けたい」
そう願う方はとても多くいらっしゃいます。
慣れた地域、子どもの学校、近所との関係…。
暮らしの土台を大きく変えるのは、精神的にも経済的にも負担が大きいものです。
では実際に、夫名義の家に、離婚後も妻が住み続けることは可能なのでしょうか?
結論から言えば、「夫の同意があれば、住み続けることは可能」です。
ただし、「名義が夫のまま」という状況には、いくつもの見落としがちな落とし穴があることを、まずは知っておく必要があります。
夫婦で共有している家であれば、持分割合によって一定の権利が保たれることもありますが、夫の単独名義の家に、離婚後も住み続ける場合、妻には特別な権利があるわけではありません。
つまり、離婚後に夫が「出ていってくれ」と言えば、原則的には拒む法的手段はないというのが実情です。
だからこそ、住み続けるには、
- 夫からの同意を得ること
- その内容を書面として取り決めておくこと
がとても重要になります。
第2章:「住み続けられる方法」はいくつかある。でもリスクもある
「住み慣れた家に子どもと一緒に暮らし続けたい」
その想いを叶えるために、実際にはいくつかの方法があります。
ただし、どの方法にも一長一短があり、事前に知っておかないと後悔につながることも。
ここでは、代表的な3つの方法と、それぞれのメリット・注意点をご紹介します。
① 夫が住宅ローンを払い続ける
離婚後も夫が住宅ローンの支払いを続け、そのまま妻と子どもが住み続けるケースです。
この方法は比較的多く選ばれていますが、実は大きなリスクも…。
メリット
- 妻側が住宅費を負担せずに住める
- 子どもにとって環境の変化が少ない
デメリット・注意点
- 夫が支払いをやめたら即アウト(家が競売にかけられる可能性も)
- ローン契約上、「債務者と居住者が違う」ことが問題視されることがある
- 夫の都合で「出て行ってほしい」と言われるリスクも
「一応合意はしたけれど、あとから状況が変わる」ことはよくあります。
そのため、この方法を選ぶ場合は必ず書面に残しておくことが重要です。
② ローンや家の名義を妻に変更する
妻が新たに住宅ローンを組み直して、夫のローンを完済し、自分名義に変更する方法です。
もっとも安心できる方法ですが、ハードルも高め。
メリット
- 自分の名義になるため、安心して住み続けられる
- トラブルの心配が少ない
デメリット・注意点
- 妻が安定した収入を持ち、審査に通る必要がある
- 不動産評価額やローン残高によっては難しいことも
現実にはこの方法を選びたくても、「ローンが組めない」「審査に落ちた」というケースも少なくありません。
③ 家賃を支払って住み続ける(賃貸契約を結ぶ)
夫が家を持ち続け、妻が家賃を払って住む、という「賃貸借契約」を結ぶ方法もあります。
メリット
- 書面さえあれば、ある程度の法的保護を得られる
- 金融機関の審査が不要
デメリット・注意点
- 夫との関係性が続くため、感情的に割り切れないことも
- 契約解除されれば、退去しなければならない
この方法は「最低限の法的根拠」を作る意味では有効ですが、長期的な安心感はあまり高くありません。
どの方法を選んだとしても、共通するのは「夫名義のまま」では不安定である、という点です。
次章では、実際にどんなトラブルが起きやすいのかをご紹介します。
第3章:「住み続ける約束」は、口約束では守れない
「夫も納得してくれているし、大丈夫だと思う」
そう感じている方も多いかもしれません。
ですが、たとえ話し合いで合意していたとしても、それが書面として残されていなければ、あとから「言った・言わない」の争いになる可能性は十分にあります。
● なぜ「書類にしておくこと」が大切なのか?
離婚直後は、お互いに冷静で「穏便に済ませよう」と思っていたとしても、
数年後、生活状況が変われば、夫の考えも変わるかもしれません。
- 再婚した
- 転勤で家を売りたいと言い出した
- 住宅ローンの返済が難しくなった
そういったとき、「そんな約束はしていない」と言われれば、書面がなければ反論のしようがありません。
● 公正証書で残すという選択肢
離婚時に取り決めた内容を公正証書として残すことで、
将来的にトラブルが起きたときにも、「証拠」として法的に活用できます。
たとえば、以下のようなことを記しておくと安心です。
- 妻が〇年間、夫名義の家に住むことを認める
- 夫が住宅ローンを引き続き返済する
- 家の名義変更についての今後の方針 など
これらは、将来「住めなくなる」リスクをできる限り減らすための、大切な備えになります。
● 離婚協議書でも良いけれど…
もちろん、離婚協議書に取り決めを書いておくことも可能です。
ただし、協議書はあくまで**当事者同士が作成する“私文書”**です。
そのため、たとえ内容が明確に書かれていたとしても、
後になって「そんな合意はしていない」と言われれば、裁判で争いになる可能性があります。
一方、公正証書は**第三者である公証人が関与して作成された“公文書”**です。
そのため、万が一トラブルになった場合も、法的な証明力が高く、「確かに取り決めがあった」ことを示す強い証拠になります。
さらに、書かれている内容によっては、**相手の軽はずみな言動を抑える“抑止力”**にもなります。
第4章:まとめ|「この家にいたい」その気持ちは、わがままなんかじゃありません
離婚は、ただでさえ心身に大きな負担を伴うものです。
そこに「家を出ていかなければいけないかもしれない」という不安まで重なると、
生活の土台が揺らぐような、言いようのない恐怖を感じる方もいるでしょう。
でも、「この家に住み続けたい」――その気持ちは、決してわがままなんかじゃありません。
子どもを転校させたくない
生活リズムを変えたくない
今ある環境を守りたい
それは、むしろ「家族を守ろうとする気持ち」そのものです。
けれど、気持ちだけでは生活は守れません。
今は納得してくれている夫も、将来何があるかは分かりません。
だからこそ、少しでもリスクを減らすために、今できる備えをしておくことが大切です。
たとえば、公正証書などの“形に残る取り決め”は、
不測の事態からあなたとお子さんを守る可能性を高めてくれます。
もちろん、それだけですべてが防げるわけではありません。
それでも、「できることはやった」と思える準備が、
いざというとき、あなたの支えになってくれるはずです。
不安なときは、一人で抱え込まず、専門家に相談してください。
あなたが安心して暮らしていけるように――
その環境を守る方法を、一緒に見つけていきましょう。
離婚公正証書や協議書の作成は、経験豊富な行政書士にお任せください。
横浜の事務所、または全国オンライン相談でお受けしています。