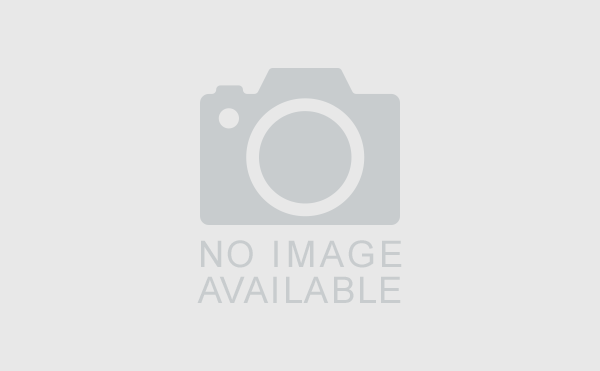離婚時の財産分与|家や車はどう分ける?公正証書でトラブル回避を
離婚するとき、感情と同じくらい大切なのが「現実的な準備」です。
特に**離婚時の財産分与**は、トラブルを防ぐためにも、知っておくべき基本があります。
「この家はどうなるの?」
「車は?生活は?」
そんな不安が頭をよぎるのは、当然のこと。
住む場所やお金、子どもの暮らし——
離婚は“心の問題”だけでなく、“生活の再設計”でもあります。
とくに「家」は大きな財産であり、名義やローンの問題も関わってきます。
また、「車も夫名義だけど私が使っている」といったケースも意外と多く、後からトラブルになることも。
この記事では、財産分与の基本と注意点、そして**「家や車をどう分けるか」**をわかりやすく解説します。
第1章|そもそも財産分与とは?どんなものが対象になる?
「財産分与」とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける制度のことです。
よくある誤解
- 「名義が夫だから、全部夫のもの」
- 「専業主婦だったから、自分には何も請求できない」
→ 実はそうではありません。
財産分与の基本ルール
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、基本的に2分の1ずつに分けるのが原則です。
どちらの名義であっても、「夫婦が一緒に生活して得たもの」であれば共有財産として扱われます。
つまり、名義が夫でも、
妻が家事や育児に専念したことで夫が働けた——その「間接的な貢献」も正当に評価されるのです。
財産分与の対象になるもの(例)
- 現金・預貯金
- 不動産(マイホーム・土地など)
- 自動車
- 家具・家電などの生活用品
- 株・投資信託・保険の解約返戻金
- 退職金(※分与対象になるかは在職中か退職済かなどを含め、条件による)
対象にならないもの
- 結婚前から持っていた貯金や財産
- 親からの相続や贈与で得たもの(=特有財産)
- 結婚後でも明らかに個人のものと認められるもの(例:高価な個人アクセサリー)
離婚の話し合いで「どこまでが対象なのか?」が曖昧なままだと、
後から思わぬトラブルになることもあります。
まずは、「これは共有財産か?個人のものか?」という視点で整理してみましょう。
財産分与に関する重要な注意点
請求には期限があります
・離婚成立から2年以内に請求しないと、権利を失ってしまう可能性があります。
※ただし「調停等」で争った場合は時効が中断することもあります。
税金は原則“非課税”
・財産分与で受け取った財産には、基本的に税金はかかりません。
・ただし、もらいすぎと判断された場合や“税金逃れ目的の離婚”と疑われた場合は、贈与税の対象になることがあります。
第2章|家は誰のもの?財産分与で家を分けるときの注意点
離婚後、「家は誰が住み続けるのか」は大きな問題です。
財産分与で家を扱う場合、名義やローンの状況によって対応が変わります。
「この家、夫名義だから、離婚したら私が出ていくしかないんですよね…?」
実はこうしたご相談はとても多いです。
でも結論から言えば、「名義が夫だから=夫のもの」ではありません。
名義よりも大切なのは「婚姻中に築いた財産かどうか」
たとえば、結婚後に住宅ローンを組んで購入した家。
名義が夫でも、婚姻中の収入で返済していたなら、共有財産と見なされ、妻にも“半分の価値を受け取る権利”があります。
ローンが残っている家はどうする?
家にローンが残っている場合、**名義変更や支払い方法の取り決め**が重要です。
離婚後も妻が住む場合は、ケースによって、いくつかの選択肢があります。
- 家を売却し、ローン残債や売却益を分け合う
- 妻が住み続けて、ローンは夫が払い続ける(要合意)
- 妻が名義を引き継いでローンも返済する(金融機関の審査あり)
ただし、住宅ローンの名義変更や残債処理には、金融機関の承認が必要です。
また、感情的なこじれで合意が難航することも少なくありません。
子どもがいると「住み続けたい」と考える方も
離婚後も今の家に住み続けたい」と希望する方は多くいます。 しかし、住み続けるためには、名義や費用負担の合意をきちんと書面にしておくことが大切です。
お子さんがいる場合、転校や引越しを避けたいという思いから、
「今の家に住み続けたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、口約束だけでは危険です。
「住んでていいって言ったじゃない!」
「そんな話はしてない。出ていってくれ」
こんなトラブルが実際に起きています。
だからこそ「書面に残す」ことが大事
話し合いの結果は、必ず書面にしておきましょう。
たとえば、次のような点は明文化しておくべきです。
- 誰が住み続けるのか(期限付きか、無期限か)
- 名義やローンをどうするか
- 固定資産税などの費用負担は誰か
これは「揉めないため」だけでなく、あなたとお子さんの生活を守るための備えでもあります。
なお、こうした「住む人・費用負担・名義」についての合意は、口約束ではなく**離婚公正証書として残しておくと、将来のトラブルを防げます**。
特にお子さんの生活環境を守るためにも、“法的効力のある書面化”は重要です。
第3章|車や家具・家電も“分け方”を決めておこう
離婚の話し合いでは、「家」や「お金」ほどではないものの、車や家具・家電などの“生活に必要なもの”の分け方も意外とトラブルのもとになります。
「それくらいは後で話せばいいか」と思っていると、いざ離婚後に揉めるケースも少なくありません。
車は誰のもの?
離婚時、車の名義が夫になっているケースはよくあります。
けれど、名義だけで「夫のもの」と判断するのは早計です。
結婚後に購入し、家族で使っていたのであれば、車も「共有財産」として財産分与の対象になります。
よくあるパターン
「夫名義だけど、ずっと私が送迎や買い物に使ってた」
このようなケースでは、「離婚後もその車を使いたい」と考えるのが自然です。
しかし、取り決めをしておかないと、後から「返して」と言われて困ることに。
車にローンが残っている場合の注意点
車のローンが残っているときは、さらに注意が必要です。
たとえばこんなケース:
- 名義は夫
- ローンの契約も夫
- 使用者は妻(保育園送迎などで使っている)
このような場合、誰がローンを支払い続けるのか、車の名義はどうするのかをはっきりさせておかないと、後々のトラブルにつながります。
注意しておきたいポイント
- ローン契約には「譲渡不可」の条項があることが多く、勝手に名義変更できない
- 車を妻が引き継ぎたい場合、ローン会社(信販会社やディーラー)の承諾が必要
- 名義が夫のままだと、離婚後に「やっぱり返して」と言われるリスクがある
- ローンを夫が支払い続ける合意をしても、口約束では法的な強制力がない
トラブルを防ぐためには?
車に関して取り決めをする場合は、以下の点を必ず確認・合意しておきましょう:
- ローンの名義と残債状況の確認
- 誰が使用・所有するかの明確化
- 誰が支払いを続けるか
- 必要があれば、車の名義変更・ローン契約の見直し
そして、こうした合意内容は離婚協議書や離婚公正証書にしておくと、後からの「言った・言わない」を防げます。
家具・家電などの生活用品も忘れずに
「大型テレビは俺が買った」「勉強机は子どもが使うから置いていってほしい」——
こうしたやり取りも、離婚の現場ではよくある話です。
特に、子どもがいる場合は学習机やベッドなど「子どもが使うもの」については、感情面も絡み、揉めやすいポイントになります。
家具・家電を分けるときのポイント
- 結婚後に購入し、夫婦や家族で使用していたものは共有財産の可能性
- 高価な家電や家具は、購入時期・使い方・希望者を基に公平に話し合う
- 勝手に持ち出すのはNG! 書面での合意・記録を残しておくと安心
書面に残す=あなたと子どもの生活を守ること
車も家具・家電も、名義や使用状況を明確にし、**「誰が、何を使うのか」**をはっきりさせることがとても大切です。
そして、「これは私が使うって言ったよね?」のような口約束では、残念ながら法的には証拠になりにくいのが現実です。
だからこそ、離婚協議書や公正証書にして書面に残すことが、あなたとお子さんの新しい生活を守る第一歩になります。
まとめ:小さな“モノ”の整理が、安心のカギに
離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためには、
家やお金だけでなく、車や家財などの身の回りの“暮らしの道具”もきちんと話し合っておくことが必要です。
特に、車のローンが絡む場合や、子どもが使う家具家電がある場合は要注意。
目の前の感情だけでなく、これからの生活を見据えて、丁寧に準備していきましょう。
家も車も、生活の一部。
だからこそ「書面」で守ることが大切です。
トラブルを防ぎ、安心して新生活を始めるために——