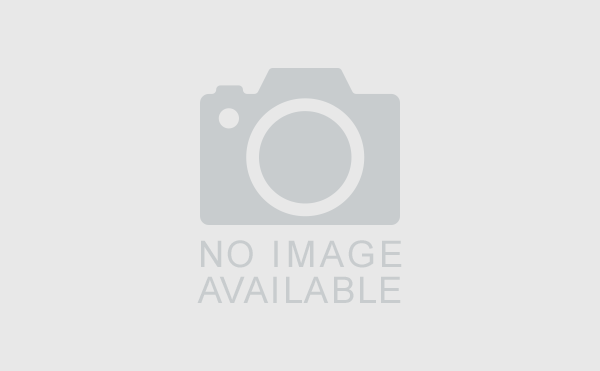離婚公正証書の作成は
難しくない!
安心して進めるための
流れと注意点とは?
離婚が決まったとき、多くの方が「子どものためにも、きちんと取り決めておきたい」と考えます。養育費や財産のことをしっかり書面に残しておけば、後々のトラブルを防ぐことができます。
そんな中、「公正証書がいいらしい」と耳にしたものの、
- 公正証書ってどうやって作るの?
- 行政書士に頼めるの?
- 手続きや費用が不安……
と、わからないことだらけで不安になる方も少なくありません。この記事では、離婚時に作成する公正証書について、行政書士の視点からその流れと注意点をやさしく解説します。
公正証書とは?
あらためておさらい
離婚後のトラブルを防ぐために、多くの専門家が勧めているのが「公正証書」です。
けれども「名前は聞いたことがあるけれど、実際どういうものなのかはよくわからない」という声も少なくありません。ここでは、公正証書の基本と、そのメリットをわかりやすく解説します。
公正証書とは?
公正証書とは、公証人(元裁判官や検察官など法の専門家)が法律に基づいて作成する、強い証明力を持った文書のことです。一般的な私文書とは異なり、第三者である公証人が関与するため、信用性・証拠力が高く、法的にも非常に強い効力を持ちます。特に離婚においては、次のような効力が注目されます。
強制執行ができる!
養育費や慰謝料、財産分与などの「金銭の取り決め」が記載された公正証書には、強制執行認諾文言を入れることができます。これが入っていれば、支払いが滞った場合、裁判を経ずに差押え(給与・預金など)が可能となります。つまり、「もし約束を破られても、すぐに動ける」安心が得られるというわけです。
裁判を起こす必要がない
離婚協議書(私文書)だけでは、相手が支払いをしない場合、裁判をして判決を得る必要があります。
そのため時間もお金もかかり、精神的負担も大きくなってしまいます。一方、公正証書があれば、裁判を経ることなく法的手続きを取ることができるため、万が一のときでも、迅速な対応が可能です。
公正証書の作成の流れ
(行政書士に依頼した場合)
はじめての方にもわかりやすいよう、行政書士に依頼したときの一般的な流れをご紹介します。
ヒアリング
離婚後の取り決めについて、次のような内容を丁寧に確認します。
- 子どもの人数・年齢
- 養育費の金額・支払い期間・方法
- 財産分与の内容(不動産・預貯金など)
- 面会交流の頻度と方法(宿泊の有無・送迎方法など)
- 学費や医療費などの“特別費用”の分担
- 慰謝料、年金分割、住宅ローン処理、姓の変更など
行政書士は、漏れやすい項目や、後々の争点になりやすい点を丁寧に拾い上げていきます。
原案作成
決まった内容をもとに、公証人に提出する「原案(下書き)」を行政書士が作成します。誤解を招かず、法的に通用する表現で仕上げていきます。
公証人との調整
作成した原案をもとに、公証人と内容の最終確認や微調整を行います。ご本人が直接やり取りする必要はなく、行政書士が対応します。
公証役場での署名・捺印
当事者双方で公証役場に行き、署名・捺印をします(※相手が来られない場合は、行政書士による代理出頭も可能です)。
完成・受け取り
署名が終わると、公正証書が完成します。
- 原本は公証役場に保管
- 正本・謄本は双方が持ち帰ります
万が一の紛失や改ざんリスクを防ぐ、信頼性の高い文書として保管されます。
★実務ポイントまとめ
- 全国どこの公証役場でも作成OK(遠方の場合でも対応できます)
- 出頭代理制度で、相手が来られない・来たくない場合にも対応可能
- 行政書士に依頼することで、法的な整理や実務的な注意点もフォロー可能
公正証書を作っただけでは不十分?!交付送達の重要性
実はもう一つ、公正証書を作成したあとに忘れてはいけない手続きがあります。
それが「交付送達(こうふそうたつ)」です。
これは、公正証書の写しを相手に「公証人の名前で」正式に送ってもらう手続きのこと。この手続きをしておかないと、いざ養育費が滞ったときに、裁判所で差押えの申立てができなくなる可能性があります。
- 公正証書を作っただけでは不十分
- 相手に“届いた”ことを証明するために「交付送達」が必要
同席できるなら当日がおすすめ
もし相手(たとえば元夫)が公証役場に来てくれるなら、その場で公証人が手渡すだけで交付送達は完了します。
郵送費もかからず、その場で証明書ももらえます。
逆に、後日に送る場合は、特別送達郵便で発送することになり、費用がかかる・住所が変わって送れない・相手が拒否するなどのリスクも出てきます。
注意したいのは、公正証書作成当日に相手(債務者)が公証役場に来ていないと、交付送達はできないという点です。
「せっかく作ったのに執行できない…」という事態を防ぐためにも、作成と同時に交付送達まで済ませておくのがおすすめです。
具体的に注意すべき
3つのポイント
- 強制執行認諾文言が正しく入っていないと、差押えができません
- 一度作成した公正証書は、変更には再度手続きが必要です
- 学費・医療費など将来かかる費用は、できるだけ具体的に取り決めておくと安心です。
このような疑問や注意点を事前に
把握し、正しい形で進めることが、
公正証書を“安心の備え”として
機能させるカギになります。
まとめ
離婚にともない、きちんと取り決めをしても、それが実行されなければ意味がありません。
公正証書は、約束を「守らせる力」を持たせるための有効な手段です。
- 裁判なしで差押えが可能
- 公証人の立ち会いで証明力が強い
- 将来のトラブル予防につながる
「こんなことになるなら、最初から公正証書にしておけばよかった…」
そんな後悔をしないように、ぜひ早い段階から準備しておくことをおすすめします。
内容の整理や手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家の力を借りて進めていきましょう。
あなたの新しいスタートが、安心できるものになりますように。
あなたのこれからの暮らしが、少しでも穏やかで安心できるものになりますように。
離婚公正証書や協議書の作成は、経験豊富な行政書士にお任せください。
横浜の事務所、または全国オンライン相談でお受けしています。